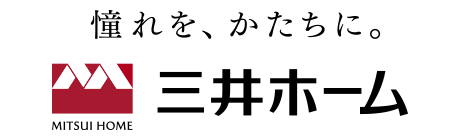2020年以降、日常的にマスクが手放せなくなりました。マスク生活によって顔の下半分が隠れるようになり、人目を気にしなくなることから、口周りの筋肉が緩んでたるみが気になっている人もいるのではないでしょうか。マスクによる弊害は見た目だけではありません。マスクで鼻と口が覆われることで呼吸がしづらくなり、無意識のうちに口呼吸になることで、全身の健康に影響を及ぼすおそれもあります。「舌エクササイズ」を取り入れて、こうした問題を解消しましょう。みらいクリニック院長の今井一彰先生にお話を伺いました。
マスクに隠れた口元に潜む危険信号

口元のたるみに悩む人が急増
新型コロナウイルス感染症を予防するための長期間に及ぶマスク生活は、私たちの健康に思いがけない弊害をもたらしています。
急増している悩みが、頬や口元の表情筋の衰えによる「たるみ」です。日常的に顔の半分を隠した状態で人目にさらされないことが当たり前になりました。筋肉が緩んだ状態が続いて表情筋が衰えたことから、肌の張りや弾力が失われて口角が下がり、ほうれい線が深くなるなど、老け込んだ印象になって悩んでいる人が増えています。
さらに、口元と鼻がマスクで覆われることで息がしづらくなり、知らず知らずのうちに口呼吸になってしまいます。口呼吸も、舌の筋肉が衰えてあごが下がりやすくなるため、たるみやしわの原因になります。また、口呼吸は多くの不調を引き起こすことも分かっています。
口呼吸は、思いがけない不調の原因に
なぜ口呼吸が不調の原因になるのでしょうか。
鼻呼吸の場合、鼻から入った空気は、鼻毛や鼻水、鼻粘膜などの働きで、空気中に含まれるゴミやウイルスが除去され、体温に近い温度と適度な湿度に調整されます。いわば、鼻がフィルター、エアコン、加湿器の3役を果たしているのです。さらに、呼吸のたびに副鼻腔の粘膜からは一酸化窒素が分泌され、気管支や血管を広げる拡張作用、病原菌を死滅させる殺菌作用が働きます。
しかし、口にはこうした空気の状態を調整できる機能がありません。外界の空気を雑菌やウイルスごと取り込むことになるので、口腔内が乾燥しやすくなり、口の中の雑菌が増えて口腔内の環境を悪化させることになります。
口腔内の環境が悪化すると、虫歯や歯周病、口臭といった口内トラブルが生じやすくなります。就寝時のいびき、夜間頻尿、肩や首回りのこり、疲れやすいなどの体調不良につながることもあります。成長途中の子どもの場合は、歯並びにも大きく影響します。
さらに、細菌やウイルスが直接体内に入り込むことで、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなるほか、免疫力低下や炎症につながることから、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患、関節リウマチなどの自己免疫疾患、うつ病などの精神神経疾患にも影響があると考えられています。
自分でできる口呼吸のチェック
自分が口呼吸になっていないか、チェックしてみましょう。4個以上当てはまる場合は、口呼吸の癖が付いている可能性があります。意識的に鼻呼吸を心がけてください。
- 朝起きると、口が乾いている
- 朝起きると、喉がイガイガする、痰がからみやすい
- 気がつくと、口を開けている
- いびきや歯ぎしりがある
- 口内炎ができやすい
- 歯に色や歯石がつきやすい
- 歯肉が腫れやすい
- 虫歯ができやすい
- 舌の横に、歯形(歯のあと)がついている
- 舌が上あごについていない
- 鼻が詰まりやすい、鼻炎がある
- 花粉症がある
- 口の中がネバネバする、口臭がある
- 唇が乾いている、唇が荒れやすい
- 口を閉じたとき、あごに梅干しのような膨らみとシワができる
- 食べるときに音を立てている
- おしゃべりが好き
- 歌うことや、管楽器を吹くのが趣味
- 激しい運動をしている
- たばこを吸っている
参考:今井一彰・中島潤子著 あいうべ協会編『世界一簡単な驚きの健康法 マウステーピング』(幻冬舎)
口呼吸を防ぐための健康習慣

筋力アップで健康にも美容にも効く「あいうべ体操」
口呼吸にならないようにするには、無意識下でも口を閉じた状態となるように、舌を支える筋力を維持することが大切です。口が閉じていれば、自然と鼻呼吸が促されますし、美しい口元づくりにも役立ちます。
「あいうべ体操」は、舌を支える筋肉を鍛えられる、簡単なエクササイズです。次の①から④までを1セットとして、毎食後に10回ずつ、1日30回を目安に続けてみてください。声は出しても出さなくてもOKです。
①「あー」と、口を大きく開く

②「いー」と、口を大きく横に広げる
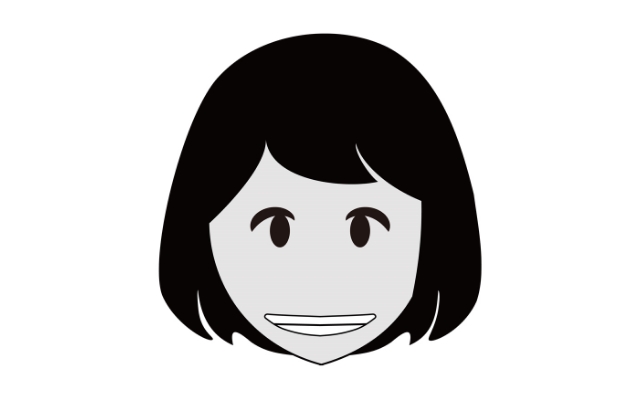
③「うー」と、口を強く前に突き出す
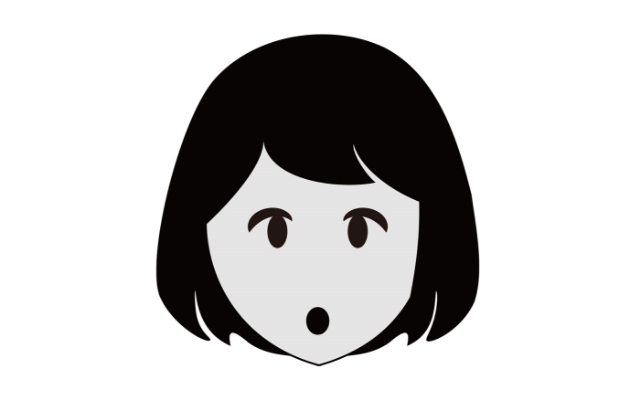
④「ベー」と、舌を突き出して下に伸ばす

ポイントは、ゆっくりと大きく口周りの筋肉と舌を動かすことです。1文字あたり1秒程度、1セット4~5秒かけて行ってください。継続することが大切なので、食事の後に限らず、朝起きたとき、歯磨きの後、入浴中など、自分のタイミングで日常生活に組み入れていきましょう。
3週間ほど経つと効果を実感できるようになります。血流が良くなって体調が良くなるほか、口周りがスッキリした、ほうれい線が薄くなったと感じることもあるでしょう。鼻づまりがおさまり、いびきが止まってよく眠れるようになるなど、気になっていた症状が改善される人もいます。
マスク下でも人に気付かれない「ベロ回し」
外出中でも、人に気付かれずにやりやすいエクササイズが「ベロ回し」です。
口を閉じた状態で、上下の歯の表面をなぞるように、舌をゆっくり大きく回します。左右5回ずつ、計10回行いましょう。舌を支える筋力アップが期待できます。

日常生活でできる、舌を鍛えて口呼吸を防ぐ工夫
エクササイズ以外にも、舌や口周りの筋力を鍛える方法があります。例えば、「噛む回数を増やせる食事」を心がけましょう。特別な献立を考えなくても、次のようなことを意識してみるだけでも自然と噛む回数が増え、口の中の筋力を鍛えられます。
- ■噛む回数を増やす工夫
- ・食材の切り方を大きくする
- ・野菜は皮ごと調理する
- ・歯ごたえのある食材を使う
- ・こんがりと焼き目を付ける
- ・飲み物で流し込まないようにする
また、寝ている間に口が開かないようにテープで留める「マウステープ」も、口呼吸防止に効果的です。医療用のサージカルテープを5cmほどの長さに切って、口の真ん中に軽く貼り付けるだけです。市販されている専用テープを用いても構いません。息ができなくなる心配はありませんが、怖いと感じる場合は就寝時に、マスクから鼻を出してあごに引っかける、「口マスク」から始めてもいいでしょう。
寝るときの姿勢も、寝返りを打ちやすいように柔らかすぎない寝具で、横向きに寝るようにすると、いびき防止につながります。また、寝ている間のことは自分では分かりづらいので、いびきを録音できるスマートフォンのアプリなどを用いて、睡眠中の自分の様子を確認してみることもお勧めです。
鹿児島県出身。山口大学医学部卒業後、同大学救急医学講座入局。福岡徳洲会病院麻酔科、飯塚病院漢方診療科医長、山口大学総合診療部助手などを経て、2006年みらいクリニックを開業。日本東洋医学会認定漢方専門医。認定NPO法人日本病巣疾患研究会副理事長、日本加圧医療学会理事。息育指導士を養成する講座を主催している。『世界一簡単な驚きの健康法 マウステーピング』(幻冬舎)、『足腰が20歳若返る 足指のばし』(かんき出版)ほか著書多数。